はじめに
ワンルームマンション投資は儲からない、やばいと言われ、インターネット上には何百万円もの負債を抱えてしまったという体験談が多数あります。私自身も「ワンルームマンション投資はやめておけ」という話を以前から知っていましたし、多額の負債を抱えて不動産業者が利益を得るスキームだと認識していました。
それでも、ある日突然のインターホンから始まった勧誘に、興味本位で応じてしまったことがあります。明らかに損をするものに手を出してしまう人がいる理由を知りたかったのもあり、警戒しながらも不動産投資の勧誘を受けることにしました。今回はその体験を通して、営業の中で使われていた心理効果と、それにどう影響されたかを整理しながら、同じような状況に巻き込まれ、負債を背負わされないための注意点を共有します。
記事内で登場する心理学効果一覧
本記事では表1に記載の心理学効果が登場します。
読み飛ばしても問題ありませんが、興味のある方は各効果の意味を確認してみてください。
| 心理学効果・原理 | 意味・概要 |
|---|---|
| バーナム効果1 | 誰にでも当てはまるような表現を使い、「自分に当てはまっている」と思わせる効果。 |
| プライミング効果2 | 事前に提示された情報が、その後の判断や行動に無意識に影響を与える効果。 |
| 一貫性の原理3 | 自分の過去の発言や行動と矛盾しないように振る舞う傾向のこと。 |
| ブーメラン効果4 | 過度な説得を受けると、かえって反発し、逆の意見を強めてしまう現象。 |
| ザイオンス効果(単純接触効果)5 | 繰り返し接触することで高感度が上がる効果。 |
| スリーパー効果6 | 疑わしい情報でも、時間が経つと信頼性を高めてしまう効果。 |
| ツァイガルニク効果7 | 途中で終わったことや未完成のものに興味が惹かれる効果。 |
| サンクコスト効果8 | 既に費やしたコストを無駄にしたくないという心理が働き、非合理的な決断をしてしまう現象。 |
| バンドワゴン効果(社会的証明の原理)9 | 多数の人がとった行動や判断を正当なものだと信じ、自分もそれに従ってしまう心理のこと。 |
| ハロー効果10 | 外見や肩書など一部の目立つ特徴が全体の評価に影響を与える効果。 |
アンケートから不動産投資の勧誘へ
不動産投資の説明を聞くまでの流れ
仕事終わりの夜、自宅のインターホンが鳴り、「簡単なアンケートに答えてほしい」と声をかけられました。個人情報を書く欄もありましたが無記名でもいいので、アンケートの回答だけお願いしますとのこと。内容は「老後の不安」や「資産形成の必要性」についてのものです。
回答を終えると、相手の人から次のように言われました。
「やはり老後の資金に不安がありますよね。だからこそ投資でお金が増えたら安心につながりますよね。実は弊社では不動産投資を扱っているのですが、ご興味があれば詳しい説明を受けてみませんか?」
ここで「お願いします」と答えると、「では後日、ご都合のつくお時間で説明いたします。お名前とご住所、ご連絡先の記入をお願いします」と言われて個人情報の記入を求められました。
一連のやりとりで使われていた心理学効果
この一連のやりとりには、複数の心理学的なテクニックが使われていたと考えられます。主なものは以下の3つです。
バーナム効果:誰にでも当てはまる内容で納得させる
アンケートの内容は誰が回答しても「はい」を選ぶようなものばかりでした。1つ例を上げると、「資産形成につながるなら投資をしてみたいですか?」のようなものです。資産を増やせるなら誰だって投資をしたいって思いますよね。
こうした設問に答えることで、投資の提案が自分に合っているかもしれないと錯覚しやすくなります。
プライミング効果:あらかじめ投資を意識させる
「老後の資金は不安ですか」といった不安を刺激する質問や、「資産形成につながるなら投資をしてみたいですか」といった問いかけにより、自然と投資=解決策だという意識を強めていきます。
これにより、不動産投資という提案が登場したとき、心理的に受け入れやすい状態にされていたのです。
一貫性の原理:一度「興味がある」と言った手前、断りづらくなる
資産形成のための投資に前向きであるとアンケートで回答すると、「不動産投資はどうですか?」という提案を断りにくくなります。
これは、一度前向きな意思を示したことと矛盾しないように行動しようとする、一貫性の原理が働いている状態です。また、「自分から投資に興味を示した」という構図を作ることで、相手から押しつけられたと感じにくくなり、断ったときに心理的に不快感が生じるブーメラン効果も避けられています。
時間をかけて行われた不動産投資の説明
不動産投資の説明の流れ
不動産投資に関する説明は、1回あたり約2時間、合計3回にわたって行われました。主な内容は以下の通りです。
- 1回目:不動産投資のメリット
- 2回目:不動産投資のデメリット
- 3回目:物件の紹介と具体的なシミュレーション
これらの内容自体は、インターネットで簡単に得られる情報と大きな差はありませんでした。にもかかわらず、説明の場には物件を購入させるための仕掛けが潜んでいました。
一連のやりとりで使われていた心理学効果
この説明の過程でも、いくつかの心理学的テクニックが巧妙に使われていました。
ザイオンス効果とスリーパー効果:繰り返し接触で信頼を獲得する
説明が3回に分かれていたのは、営業担当者への親近感を高め、不動産投資への疑念を薄れさせるためだったと考えられます。実際には、3回で合計6時間に及ぶ説明が行われ、話の進み方は非常にゆっくりでした。
こちらが「もっと早く説明を終えてほしい」と伝えても、「きちんとご理解いただきたいので」と返され、予定通りのペースで話を続けられました。
それにもかかわらず、最後の物件シミュレーションの場面では、じっくり考える余裕を与えられないまま契約するかどうかの判断を迫られましたが。。。
ツァイガルニク効果:途中でやめにくくなる仕組み
1日目にメリットを聞かされると、「じゃあデメリットはなんだろう?」と思うはずです。さらに、メリットとデメリットを聞いた後は、「実際、どんな物件で、どれぐらいの利益になるのだろう?」と思うはずです。
一度話を聞いてしまうと、途中離脱しづらくなります。説明の長さに多少ストレスを感じても結局最後まで聞いてしまうことになってしまうのです。
サンクコスト効果:かけた時間を無駄にしたくない心理で判断を鈍らせる
長々と説明を聞かされることで、「今まで使った時間を無駄にしたくない」という気持ちが働き、よりいっそう途中で断ることが難しくなります。
このような気持ちは、物件の購入を決断する場面にも影響します。費やした時間に対して「何かを得たい」と感じることで、明らかに非合理的な購入を選択してしまう可能性があります。
購入物件の提示
物件提示時のやりとり
物件の紹介に先立ち、「ローンが組めるかを確認するため」として年収を尋ねられました。
(2回目の面談の際に、「次回、源泉徴収票をお持ちください」と依頼されていましたが、会社名を知られたくなかったため、忘れたふりをして年収のみを伝えました。)
年収を伝えると、業者は
「あなたの年収であれば、十分対応可能です。これだけのご年収だと非常に低い利息でローンが組めるはずです。これだけ良い条件で借りられるのは一部の限られた方だけです。ぜひこのチャンスを無駄にしないでください」
と強調しました。さらに、
「同じようなご年収の方だと、少し期間を空けて追加で物件を購入されるケースも多いです。多い方だと5件、6件と所有されている方もいらっしゃいます。」
と追加説明されました。
その後、「こちらの物件でシミュレーションしてみます。」と言いながら物件情報を提示してきました。
提示された内容には、想定家賃収入や、固定資産税、修繕積立金、火災保険料などの費用が含まれており、それに基づいた月々の収支について説明が行われました。
質疑応答が一通り終わると、次のように問いかけられました。
「それでは、こちらの物件をご購入されますか?」
やり取りで使われていた心理学効果
「これだけのご年収だと非常に低い利息でローンが組めるはずです。限られた方しか持てないこのチャンスを無駄にしないでください」
これは心理テクニックとして、特別感を出して購買意欲を高めていますが、その他にも以下のような心理学効果が使われています。
バンドワゴン効果(社会的証明の原理):周囲に同調する心理を利用
「同じようなご年収の方だと、少し期間を空けて追加で物件を購入されるケースも多いです。多い方だと5件、6件と所有されている方もいらっしゃいます。」
この発言は、「すでに多くの人が実践している」という印象を与え、購入に対する安心感を演出するものです。
実際には「利益が出ている」とは一言も言っていないにもかかわらず、「みんながやっているなら自分も大丈夫だろう」と思い込まされてしまいます。
ハロー効果:話し手の自信が提案内容の評価に影響する
提示されたシミュレーション結果は、毎月数千円の赤字になるというものでした。
これは、いわゆる「キャッシュフローがマイナスになる物件」であり、後に負債に苦しむケースでもよく見られるパターンです。
しかし、説明していた担当者は非常に自信に満ちた様子で、
「支払いが完了すれば、この物件はあなたのものになります。」
と堂々と話していました。こうした態度に引きずられ、「よく分からないけど大丈夫そうだ」と誤った安心感を持たされてしまうのが、ハロー効果の典型例です。
振り返ってみて
最終的に私は契約を断りましたが、一瞬「もしかしたらこれって良い話なのかも?」と思ってしまったのも事実です。自分では冷静なつもりでも、段階的に心理的な影響を受けて判断が揺らいでいたことを実感しました。
あらかじめ「これは良くない投資だ」と理解していたはずなのに、それでも判断がぶれてしまう。それだけ心理的な働きかけというのは強力なのです。
対処法
このような心理テクニックを利用した誘導に騙されないためには、テクニックの種類を知っておくことに加えて、以下の点にも注意が必要です。
- インターホンでの営業には対応しない
訪問営業は、相手のペースで会話が進みやすく、こちらの警戒心が揺らぎやすくなります。最初から関わらないのが最も安全です。宅配業者や、近隣住民の挨拶など、明確な目的がある場合を除いて、インターホンには応じない姿勢を貫きましょう。 - 「話を聞くだけ」のつもりでも、興味本位で関わらない
「ちょっとだけなら…」と話を聞いてしまうと、無意識のうちに「投資してもいいかもしれない」と思い始めてしまいます。最初の接触がすべての入口になる——その意識を持つことが大切です。 - よく理解していないものは絶対に契約しない
説明を受けたことで「理解した気」になってしまうことがありますが、わからないものに手を出すのは厳禁です。すぐに決断を迫ってくるようなケースには、「冷静な判断をさせないための演出」である可能性があります。少しでも納得できない点がある場合は、必ずその場で立ち止まりましょう。
結論
不動産投資そのものがすべて悪いというつもりはありません。実際に成功している人もいるはずですし、適切な知識と判断力があれば、有効な資産形成手段になり得ます。
しかし、今回のような訪問営業や強引な勧誘では、心理的テクニックを駆使してこちらの判断を揺るがせ、「自分で納得して決断した」と思わせる仕掛けが多く含まれています。
気づかないうちに、冷静な判断ができなくなっていることが最も危険なのです。
このような場面で本当に大切なのは、
- 自分の価値観や判断軸を見失わないこと
- その場で即決せず、必ず時間をおいて冷静に考えること
- わからないことには手を出さないこと
この3点に尽きます。もし少しでも「変だな」「話がうますぎるな」と思ったら、その感覚を信じて一歩引くことが、自分自身とお金を守るための第一歩です。
参考URL:
- 「バーナム効果」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2025年4月6日 (日) 22:27 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/バーナム効果 ↩︎
- 「プライミング効果」『脳科学辞典』。 2025年4月20日 (日)、URL: https://bsd.neuroinf.jp/wiki/プライミング効果 ↩︎
- 「一貫性の原理」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2024年6月12日 (水) 03:06 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/一貫性の原理 ↩︎
- 「ブーメラン効果」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2024年12月3日 (火) 21:54 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/ブーメラン効果 ↩︎
- 「単純接触効果」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2024年5月30日 (木) 13:03 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/単純接触効果 ↩︎
- 「スリーパー効果」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2024年4月30日 (火) 03:06 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/スリーパー効果 ↩︎
- 「ツァイガルニク効果」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2024年5月28日 (火) 15:04 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/ツァイガルニク効果 ↩︎
- 「サンクコスト効果」『錯思コレクション Collection of Cognitive Biases』。2025年4月20日 (日)、URL: https://www.jumonji-u.ac.jp/sscs/ikeda/cognitive_bias/cate_d/d_21.html ↩︎
- 「バンドワゴン効果」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2025年3月16日 (日) 04:43 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/バンドワゴン効果 ↩︎
- 「ハロー効果」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2024年12月7日 (土) 19:03 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/ハロー効果 ↩︎
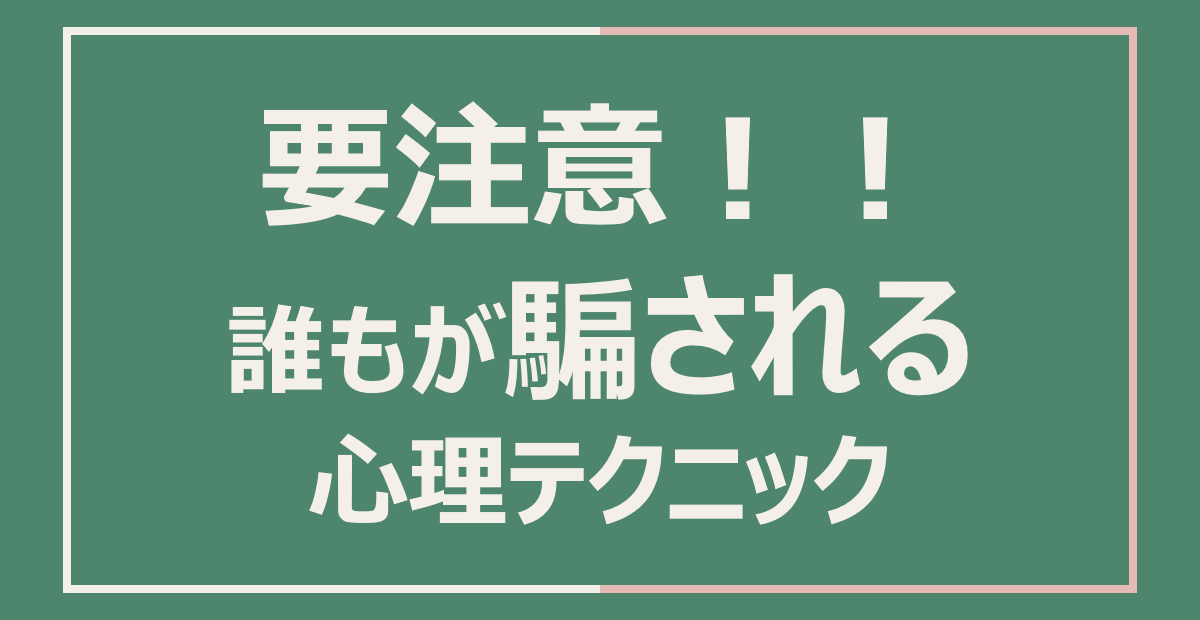
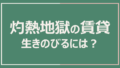
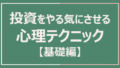
コメント